※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています
JR西日本の美祢線(厚狭~長門市間)が、被災からの復旧を断念し、バス高速輸送システム(BRT)への転換が決定したとの報道がありました。

BRTについては最適解だったと思いますし、私は賛成です。
それにしても日本の地方交通が抱える根深い問題が、この美祢線のケースには凝縮されているように感じます。
美祢線の歴史
美祢線は、石炭輸送のために敷設された歴史を持つ路線です。

かつては美祢炭田からの石炭を瀬戸内海へと運び出す重要な産業動脈として機能し、その歴史を物語るかのような力強い橋梁やトンネルが点在していました。
厚狭駅で山陽本線から分岐し、中国山地の懐へと分け入り、やがて日本海側の長門市へと至るその路線は、車窓から見える穏やかな田園風景や山間の景色があります。
私自身、美祢線には2013年に一度だけ、長門市駅から厚狭駅まで乗車した経験があります。
あの時の旅情を思い出すと寂しさは募りますが、今となっては「乗っておいてよかった」という安堵の気持ちも同時に湧き上がってきます。
豪雨災害の甚大な被害と復旧困難な厳しい現実
しかし、その美祢線に決定的な打撃を与えたのは、2023年7月の豪雨災害でした。

線路への土砂流入はもちろんのこと、特に甚大だったのが厚保駅と湯ノ峠駅の間を流れる厚狭川に架かる美祢線第1厚狭川橋梁の流出でした。
この光景は、自然の猛威が鉄道に与える影響の大きさをまざまざと見せつけるものでした。
鉄道の生命線であるインフラが破壊されれば、復旧には莫大な費用と時間、そして技術が必要となります。
ネックとなったのは輸送密度
JR西日本は当初、早期復旧を目指す姿勢を示していましたが、現実は非常に厳しいものでした。
最も大きな壁となったのは、やはり「輸送密度」という冷徹な数字でした。
美祢線の輸送密度は、災害前の2019年度でわずか280人/日。これは、地方交通線の存廃を議論する際に目安とされる「2,000人/日」を大きく下回る数字であり、JR単独での復旧が極めて困難であることを示唆していました。
鉄道事業は、路線を維持するだけでも莫大なコストがかかります。
線路や車両の保守、信号設備の維持、人件費など、運行がある限り発生する固定費は、乗客が少ないからといって劇的に減るわけではありません。
輸送密度が極めて低い路線では、運賃収入だけでは到底これらの費用をまかなうことができず、慢性的な赤字に陥ります。
このような状況で、JR西日本が完全な鉄道復旧に前向きになれないのは、企業として当然の判断と言わざるを得ません。
そこに、流出した橋梁の再建という、数億円規模とも言われる巨額の復旧費用が加わるのです。この費用を誰が負担するのか、という問題が浮上するのは避けられないことでした。
自治体の重い負担と災害リスクの激甚化
ここで重くのしかかってくるのが、地方自治体の負担です。
多くの場合、被災した地方交通線の復旧費用は、鉄道事業者と国、そして沿線自治体が応分の負担を求められます。
しかし、美祢線沿線の自治体、すなわち美祢市や長門市は、少子高齢化と人口減少に直面しており、財政状況も決して楽ではありません。
数億円、あるいはそれ以上の復旧費用を自治体単独で負担することは、市民サービスや他の公共事業を圧迫し、財政を破綻させかねないほどの重荷となります。
仮に鉄道として復旧できたとしても、その後の維持費用や設備更新費用も考慮すれば、未来永劫にわたる負担となりかねません。
住民の足を守るという使命と、限られた財源の中でどう交通インフラを維持していくかという、自治体の苦悩が痛いほど伝わってきます。
芸備線の末端区間が抱えるような、利用実態と乖離した鉄道維持の困難さを考えれば、むしろこの美祢線のBRT化の決断は英断であるとさえ言えるでしょう。
さらに、近年激甚化する災害のリスクを考慮すれば、たとえ復旧したとしても、将来にわたって再び同様の被害を受け、多大な費用と時間を要する事態に陥る可能性は否定できません。
一度ならず二度、三度と被災するリスクを抱えながら、巨額の投資を続けることは、現実的な選択とは言いがたいのです。
BRT化がもたらす可能性と利便性
そうした中で、今回のBRT化決定は、苦渋の選択でありながらも、現実的な解として受け止めるべきだと考えます。
BRTは、専用道を走行することで定時性・速達性を確保しつつ、バスとしての小回りや柔軟性を併せ持つ輸送システムです。
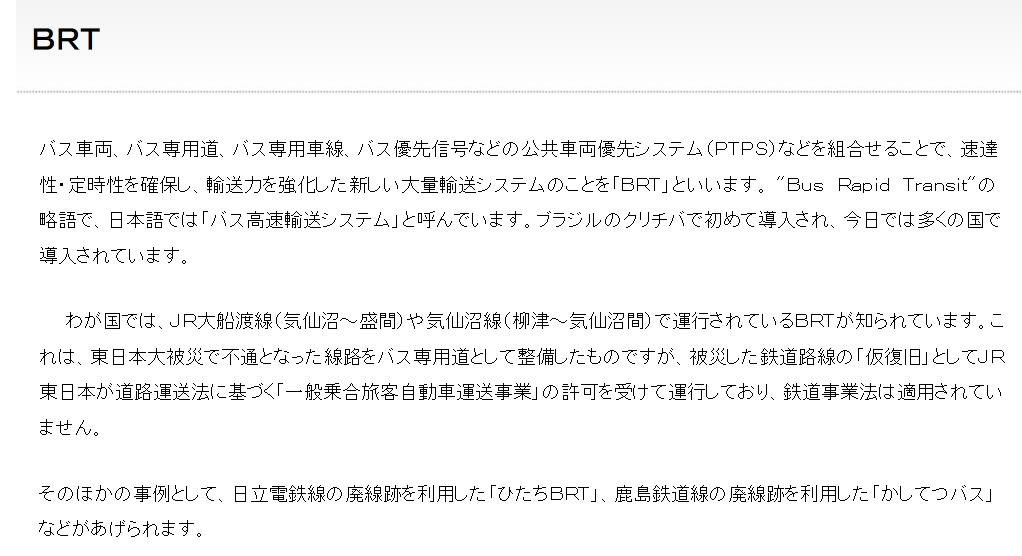
既存の鉄道用地を活用することで、インフラ整備費用を抑え、運行コストも鉄道に比べて格段に安価に抑えられるというメリットがあります。
鉄道としての線路は失われますが、少なくとも公共交通機関としての機能は維持される、これは、地域の交通網を完全に失うよりは遥かにマシだ、という判断が下された結果なのでしょう。
BRT化のメリットとは
BRTのメリットは、鉄道と比較して運行の柔軟性が高い点にあります。
需要に応じて本数を増やしやすく、また、鉄道駅のない場所にも細かく停留所を設置できるため、地域住民の利便性はむしろ向上する可能性を秘めています。
鉄道の旅情は確かに失われますが、観光客の利便性という点では、BRTが優位に立つ場面も少なくありません。
さらに、ICカード導入の面でもBRTは有利です。
既存のバス路線網との連携も容易であり、ICカードの導入も比較的容易に行うことができます。

実際、既にBRTとして生まれ変わった日田彦山線BRT「ひこぼしライン」では、全国共通ICカードが導入され、利用者の利便性が大きく向上しています。
これは、地域住民だけでなく、観光客にとっても大きなメリットとなるでしょう。
新たな時代の幕開け
美祢線のBRT化は、全国各地で厳しい状況にある地方交通線にとって、一つの「前例」となる可能性を秘めています。
災害を契機とした路線のあり方見直し、そして鉄道からBRTへの転換という選択は、今後、他の路線でも議論されることになるかもしれません。
私たち鉄道ファンとしては、失われる鉄道資産への惜別の念は尽きませんが、同時に、地域に暮らす人々の足を守り、持続可能な交通手段を確保するという視点も忘れてはなりません。
美祢線の新たな歴史は、BRTとして刻まれていくことになります。願わくは、BRTが地域の交通ニーズに応え、沿線地域の活性化に貢献し、そして何より、再び多くの人々に利用される「動く公共交通」として定着することを切に願うばかりです。
美祢線のBRT化は、決して特別な事例ではなく、今後の日本の人口減少や災害多発を考えれば地方交通が直面する現実の縮図であり、このような事例が今後も増えていくことは避けられないでしょう。
失われた鉄道風景に思いを馳せつつも、未来を見据えた地域交通のあり方を、我々一人ひとりが真剣に考える時期に来ているのかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae4b178.700ca59d.4ae4b179.0857b8f3/?me_id=1213310&item_id=18632817&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1886%2F9784839961886.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae4b178.700ca59d.4ae4b179.0857b8f3/?me_id=1213310&item_id=21654832&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6500%2F9784802216500_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

